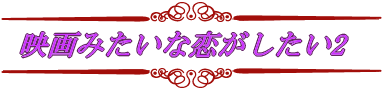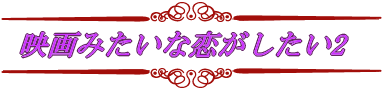バイト先で、商品を並べていたら、
「あの」と声を掛けられて、そこにおだやかーな顔をした綸同君がいたので、後ろに倒れそうなぐらい驚いたけれど、何とか体勢を立て直して、
「いらっしゃいませ」と平静を取り繕った。彼は私のそういう様子も気づかないようで、
「あの」と不思議そうな顔をしていた。
「買い物?」と聞いたら、
「いや、違うけれど」と言われてしまい、
「そう」としか言えなくて、
「ここでバイトしてるって、誰かに聞いたから、それで」
「ああ、そういえば、来たよ。誰か、ごめん、だれだったかは思い出せない」
「俺も」と言ったので二人で笑った。顔は覚えているけれど、名前が思い出せない。何しろ、理系で同じクラスにはなったことがない子だったので、顔は知ってるけどなあ……という程度しかわからない。でも、同じクラスなのに彼も分からないというところが、相変わらずだなと思えた。
「それで?」と聞いた。
「え、あ、いや。この間、会ったから、ちゃんと言っておきたかったから。でも、言えなかったから、それで、そういえば誰かがここで会ったと言っていたことを思い出して」それで来てくれたのか。彼の顔をじっと見ていたら、
「ひょっとして気にしていたんじゃないかって、森園に言われて」
「森園君?」
「そう高校の時に気にしてそばに寄らないようにしていたと教えてもらって」うーん。
「森園君がそう言ったの?」
「違うよ。大橋に会ったことを森園がクラス会で話したら、テニス部の子が教えてくれた。当時、黄和に言われたこともよく分からなくて、それを森園が話してしまって、確かめて」困ったなあ。そんな昔のことを蒸し返して話したら、あることないこと継ぎ足されて噂されそうだ。
「それで、大橋がかなり落ち込んでいたからと、それでそばに寄らないように気を付けていたと聞いたんだ。でも、途中でうるさくなって聞けなくて。本島朝日がいたから、それでよく分からないことを叫んではいたけれど、今度は誰も相手にもしてなくて」
「え、そうなの?」
「みんな自分の近況を話すことを優先していたから、高校時代のような感じではなかったからかも」
「はあ」よく分からないなあ。本島朝日は、元気よく廊下で叫ぶような男だった。いたずら大好き、お調子者。ただし、人気者ではない。『勝手にやっていて』という空気感がそこら中に漂っていた。そういうタイプだから、クラス会に来ても、女性たちは喜ばないだろう。子供すぎて。
「浮いていたんだ?」
「まあ、そういう感じなのかな。女の子たちは服装や髪形が変わりすぎていて、化粧もしていたからわからないぐらいだったし、会話の仕方もワイワイという感じじゃなくなっていたから。男の方は変わってなかったけれど」
「そう」
「それで、大橋が気にしていたのなら、謝っておきたくて」
「え、なんで、綸同君が?」
「知らなかったから」
「え、知らなくても、当然でしょ。黄和さんが言ったんだから」
「いや、えっと、ちょっと変なことを聞いてくるとは思っていたんだ。『あの子のこと、そんなに嫌いなんだ?』とか、『迷惑だったのなら言っておいてあげるからね』とか」うーん、そんなことを本人にも言っていたのか。
「当時はその言葉の意味が分からなくて、聞いても説明もよく分からないし」そうだろうな。彼女は、よく男子生徒の肩を叩いて、
「分かってるって、いいよ、いいよ。気にしなくても」と言っていた。そうして、いつの間にかいなくなり、
「お前が気にしてくれ」「一度ぐらい、人の話を最後まで聞けよ」と男子たちが怒っていたのを目撃した。聞きかじった程度の話を誤解して、勝手に人に教えてしまったり、男子生徒が困っていたら、勝手によっていき、
「なによ、なによ。なにかあったの? 困ったことがあるなら、相談に乗るよ」と言いながら、相手の話をちゃんと聞いてなくて、勝手に誤解して勝手に話を進めたり、人に言ってしまったり、ちょっと人騒がせなタイプだった。
「はっきり言って迷惑だった」とあとで男子生徒が怒っていた。なぜか、女生徒のもめごとには近寄らないので不思議だった。それでも、男子とは仲良くはしているんだろうなと勝手に誤解していたけれど、綸同君がやられたことを聞いたあとでは、ほかの男子生徒も似たような経験をしていたんじゃないかなと思えた。でも、高校時代のことを今更聞いてもしょうがないので、その話はちらっとしか聞いてない。高校時代の友達に映画のことをちょっとだけ教えるために連絡したときに、少しだけ聞いた程度だった。
「ごめん。あのとき、ちゃんと確かめておけば良かった。まさか、大橋にそんな変なことを教えているなんて思いもよらなくて」
「いいよ、もう。昔のことなんだし」
「でも、気にしていたと聞いたから」
「テニス部の子に聞いたんだ。でも、いいよ、それは済んだ話だし」
「終わったー?」と元気のいい、どこかで聞いた声がして見たら、
「ひーちゃん」と驚いた。
「あ、ごめん。まだ、言ってなかった」と綸同君がのんびりと言ったので、
「あいかわらずねえ。一緒に来たの。ここの場所がさ、分からないみたいだったから、ついでについてきた」
「あのねえ」とあきれた。ひーちゃん、こと、常陸成美《ひたちなりみ》は高校時代、仲良くしていた子だった。ただ、理系だったので、クラスは違ったけれど。
「あれ、でも、大学は安修じゃなかったよね」
「恒栄。でも、いまだに連絡取り合ってるの。綸ちゃんじゃなくて、森園の方と」
「なるほど」
「そういえば、森園君って、どこだっけ? 久我山だったっけ?」
「当たり。元気そうだね。ここでバイトしてるんだ?」と聞かれて、しばらく雑談を続けていたら、綸同君がそのまま立っているのに気付いて、
「あ、ごめん」と謝った。
「そうだ、綸ちゃん。ちゃんと誘った?」と聞いたので、何のことだろうなと、二人を見た。
「凱歌スクエアに一緒に行こうって」と言われて、驚いた。
「え、でも、あそこは」できて間もないため、人が多いと聞いていた。綸同君は、ミーハーなところはないので、そういうところに行く感じに見えなかったのでびっくりした。
「ちょうどいいじゃない。お詫びに一緒に行こうって言ってるから、由香、今度の日曜は?」と聞かれて、
「え、急に言われても」
「バイト?」と聞かれて、
「あ、いや、バイトは入ってないけど」
「じゃあ、ちょうどいいじゃない。行ってきなさい」と勢いよくひーちゃんに叩かれてしまった。 |