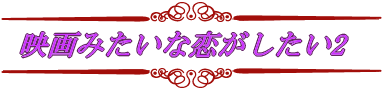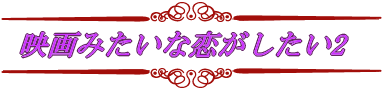「ごめん。なんだか、いつのまにかデートすることになって」
「それにしては浮かれていたように見えたけれど」
「うれしかっただけ。高校時代にあこがれていた人とデートをするってこと。考えられなかったから」
「お前の性格ならそうだろうな」
「でも、会話が続かなかった。あの人、いくら話しかけても、なんだか、こう、手ごたえがないというか」
「それは相性が悪いんだろ」
「違うんだって。森園君でも、ひーちゃんでも同じような反応みたい」
「クラゲみたいなやつかもな」
「うーん、そう言われるとそうなのかな。彼は不思議な感じかな。フワーとした優しい空気に包まれるような、そんな感じ」
「それが癒しか?」と聞かれてうなずいた。
「彼を見ていたころを思い出しちゃった」
「部活の時だろ?」
「彼を見るきっかけを思い出したの。困ることがあってね。ある先輩に色々と嫌味を言われてしまって」
「ああ、言ってたな」
「その先輩は副部長。私たちは2年になったばかり。嫌みを言った人が仕切っていたところがあるから、私は男子のそばに寄れなくて」
「それは相手が悪いんじゃないか? 後輩をいびってどうするんだよ」
「それはそうなんだけど、私が迷惑を掛けちゃったことがあって」
「それも聞いたよ。でもな、俺にはお前がそれで萎縮する必要はないと思えるぞ。さっきもそうだ。あんなに謝る必要がどこにある」
「でも、内緒で調べてしまったから。ちょっと心配で、裏でエミリと相談して」と言ったら、ため息をついていて、
「なに?」
「それで俺に電話をするのを忘れたとか言うなよ」と言われてしまい、
「ごめんなさい」と謝った。
「それもあったんだな。まったく。だとしてもメールぐらいは送れよ」
「ごめん。しづらかった」
「なんで?」
「怒っていたように思えたから」
「怒っているにきまっているだろ」
「でも、どうして怒るのかわからなくて」
「自分の彼女が浮気したら、怒るのは当然だと思うけど」と言われて、彼をじっと見てしまった。
「なんだよ?」気に入らなさそうな顔をしていたけれど、彼に言われた、『自分の彼女』という単語がうれしくて、
「え、なんで」とうつむいた。
「なんだよ、その反応は」
「え、私たちって、そういう関係?」
「どういう関係だよ」
「恋人ってことなのかな?」
「一応、そうだろう」
「一応なんだ」
「まだまだその段階だろ。お前も俺もお互いのことなんてよく分かってないんだしね」
「それはそうだけれど」
「お前はそのつもりはなかったんだな」
「え、だって、それは。はっきり言われていないから」
「気がない相手をデートに誘わないだろ」
「甲羅は?」
「あいつと一緒にするな」
「でも、良く合コンしてるし」
「お前、絶対に誤解してるだろ。俺は進んで参加したことは一度もないぞ」
「そうは思えないけれど」
「俺は甲羅とは違う。ただ、あいつに強引に誘われて、時間つぶしに行っていただけだ」
「時間つぶし?」
「家にいると居心地が悪かった時があったからな」
「え?」
「お前に話してあるだろ。兄と父は良く話すけど、弟と母親も良く話す。でも、俺はそういうところがないから」
「仲良くないの?」
「中学に入ったころからそうだったよ」
「そう」
「親族の集まりだって、参加してないし」
「親族?」
「そうだ。忘れるところだった。お前に来てほしいって」
「え、なに?」
「美弥がお前に言っておけって」
「美弥さん?」
「演奏会付の婚約パーティーだから。あいつの知り合いと身内が参加する立食パーティー。学祭の後にあるからな」
「ちょっと待って。洋服なんてないよ」
「おまえなあ。そこまでかしこまらなくても」
「え、やだ。今からなんて時間がないし。洋服だって」
「貸衣装でいいだろ。今から探せよ」
「そう言われても」
「一緒に行かないと俺が怒られるからな」
「誰に?」
「美弥に」
「どうして?」
「あいつに聞いてくれよ。美弥にしろ、長船にしろ、お前と仲直りしろとうるさくて」
「ごめんなさい」
「俺が悪いみたいだよな」
「いや、少しはあなたのせいだと思うよ」
「どこが?」
「だって、彼女だと思われているなんて、知らなかった」
「宣言しろって? 付き合ってくださいとでも言えばいいのか? それとも、好きだと言えばいいって言うのか?」と聞かれてむせてしまった。期待して彼の顔を見ていたら、
「一生言わない」とそっけなく言ったので、
「え、それはちょっと冷たいでしょ」
「違う。俺はそういう言葉にするのはダメなんだよ。態度で分かれ」
「あのー、無理」と言ったら、
「お前が相手だと疲れるよな」と言われてしまった。 |