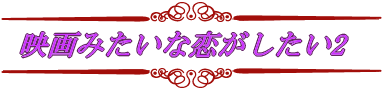
| 前へ | 次へ |
| 電話がかかってきて、切ってから、 「行こう」と花咲君が言ったために、 「え、なんだよ?」と仲島君が聞いた。 「悪い。相川ともめごとがあったみたいだから」と花咲君が言って、 「えー、ほっとこうぜ」と言ったために、 「じゃあ、俺は行ってくるよ。大橋の映画を見て、もめたらしいから」と花咲君が走り出した。 「あ、おい」「どうする?」とみんなが顔を見合わせた。 「だいたいね、あなた、いつも人のやることにケチをつけるけれど、一度でも自分の作品と言うか、打ち込んだものがあるの? それが評価されたことが」と千花ちゃんに言われて、相川が、 「あるね」と言い返していたけれど、 「ないない、ケチをつける専門」という声があちこちからしていて、相川が向きになって、 「うるさい、あるね。俺は小学校の時に」と言い出した。 「話が古い」と誰かが言って、ほとんどの人が思ったのか、その言葉にうなずいていた。相川の自慢話のほとんどが小学校の時に足が速いとほめられた。小学校の時に逆上がりが一番できた。というものだったために、 「せめて、中学からにしてくれ。運動系以外で。運動系でも部活で県内で何位以内とかそういう華々しいものなら納得するけどな」 「えー、それを言い出したら、俺も何も言えなくなるな」 「あ、俺も」とあちこちから声が上がった。 「俺さ。こうやって、記念になるというか、記憶として残せるようなものって、すごいと思うけどな。たとえ、学生レベルだとしてもさ」映像の方を指差した。イベントの準備が整わず、映像がまた流れていた。みんながそちらを見て、 「あ、あるかもねえ。大橋さんじゃなくても、私も出たいな」 「きれいなうちに、映像に自分を残しておきたい」 「自分の親に撮ってもらった運動会やイベントの映像でいいじゃん」という声もしていたけれど、 「違うってば。こうやって、違う形で映像とか、何か形に残るのがいいんじゃない。今しかできないことだしね。それを馬鹿にするっていうのは、ちょっとね。 私は好きだよ。たとえ、レベルが低くても、一生懸命作ったんだなっていうのは、見ていて分かるから」と一人の女の子が言い出して、何人かがうなずいてい た。 「へ、ばかじゃないの」とミイさんが言ったら、 「そうかしら? 確かに大橋さんのは演技と言うより、ただ自然体で映っているだけの映像とは思うけれど、彼らのことを馬鹿にすることなんて、できないと思うわ。私をはじめとしてね」と千花ちゃんが言ったので、みんなが驚いていた。 「馬鹿にしてたら、人のことを気にしてばかりいたら、何も残らない。そう教えてくれた人がいるわ。私、自分でも焦っていたと思う。大橋さんの映像を見て、 正直ショックだったわ。どこかで相川と同じような気持ちがあったから。……見るまではね」そう言ったために、さすがに相川も何も言えなくなっていて、 「な、何よ。こんな映像。かわいくもない女がそれらしく映っているだけじゃない」ミイさんが言い出したら、花咲君が近寄って、 「言いすぎだよ」と止めた。 「あ」と千花ちゃんが驚いていたけれど、 「大橋はこの撮影を頑張っていたよ。彼女なりに悩みながらもやっていたと思うしね。他のスタッフも一生懸命だった。それにね、沢登の方ではメイキング映像 を流していたけれど、彼女たちがどうやって、あの映像を作ったのか、それを見たら、そんな風に馬鹿にすることは言えなくなると思うけどね」 「メイキング映像?」とほかの子が聞いた。 「ああ、そういえば、上映の合間に映してたな。カメラテストとかしてた。大橋以外にも候補がいたみたいで、その映像も流れていたよ」と後ろから来た仲島君たちが教えていた。 「行こう」と花咲君が千花ちゃんを促していて、彼女がうなずいていた。 「奢るよ」と花咲君が言いだしたので、 「え?」と千花ちゃんが驚いていた。 「一歩進歩したから。そのご褒美」と花咲君が笑っていて、 「だったら俺、あそこの屋台の」と後ろにいた仲島君が言いだして、 「お前らは自力でどうぞ」と花咲君に言われて、 「えー、いいじゃん」とぼやいたために、みんなが笑い、段君が不思議そうに千花ちゃんを見ていた。 |