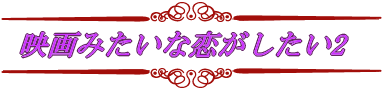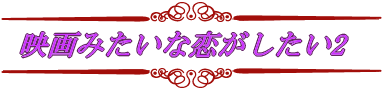反省できないのは
本屋に千花ちゃんが通りかかり、
「あら、こんなところにいたのね」と花咲君に声をかけた。
「ちょっと、調べ物があってね。図書館の本には載ってなかったんで」
「熱心ね。ねえ、食事でもしてから帰らない?」と聞いた。
「うちの母親、近所の会合で遅くなるから、食事を作れって言われたけれど、面倒だから食べていきたいの。付き合って?」
「君は弟がいるんじゃないのか?」
「あら、いいわよ。あの子だって、好き勝手してるんだから」花咲君が笑った。
「兄弟の仲は良くなさそうだね」
「そうね。会話はないわ。あの子、手ごたえがないの。牛美と同じよ」
「その呼び方はやめるように注意したはずだけど」
「ごめん、くせになってるのよ」
「その呼び方をやめると言うなら、付き合ってもいいよ」
「え?」千花ちゃんが嬉しそうな顔をした。
「ただし、聞いてほしいことがあるけどね」
「何よ、嫌なことじゃないでしょうね」とにらんでいた。
「もうちょっとおしゃれなところがいいわ」千花ちゃんが怒っていた。定食屋でかろうじて個室があるけれど、男子学生がいっぱいいたからだ。
「個室があるところがいいかと思ってね」
「だから、おしゃれで雰囲気がいいところがいいでしょ。デートで使うようなところ」
「デートだと誤解されたくないから、ここにしたんだけど」と言われて、千花ちゃんが睨んでいた。
「つくづく面白くないことをするわね、あなたは」
「誤解されると困るだろうから」
「いいじゃない。もう、どうせ、大橋さんは九条君と付き合ってるみたいだしねえ。ありえないカップルよね。九条君、悪くないけど、好みじゃないけど、まあ、いいんじゃないの。振られるのも時間の問題」千花ちゃんが言いかけたら、
「ストップ」と花咲君が止めた。
「あら、なに?」
「注意しておこうと思って。大橋のことは、これ以上は言わないこと。特に、九条とのことはね」
「あら、ひょっとして、さっきのお願いって、それ? 嫌だ。あの子の世話なんて焼く必要はないでしょ。もう、違う男の物なんだし」花咲君が笑った。
「笑い事じゃないわ。あなたも振られたってことなんでしょ」
「君まで短絡的な発想だな。大橋とは友達だから」
「ふーん、誰も信じないわよ。あなたと楽しそうに嬉しそうに話しているのを散々見てるんだもの。それが九条君といつの間にかくっついてるんだもの。映画での錯覚でしょ。映画で盛り上がったから、恋をしてると混同してるだけでしょう。そうじゃなければ、九条君はもっと綺麗な子と付き合っているわ」花咲君が笑った。
「なによ?」
「君の見方は相変わらず偏っている。聞いていると疲れてくるから、少しは控えてくれるとうれしいね」
「そう言われても、事実でしょ」
「君の解釈にはやっかみが120%以上含まれているために、事実とは異なっている。自分が気に入らない女性が幸せになるのは許せない、と言う感情が丸ごと入っているから、聞いていると嫌な気持ちになるだけだから」
「あら、どうしてよ? あの二人が付き合うのはありえないでしょ」
「九条に聞いてみたことはないだろう?」
「話したことなんてないもの」
「それなのに決めつけている。それは君の面白くない感情を混ぜて考えるから、そうなっているだけだよ。僕にはお似合いだと思う」千花ちゃんが唖然としていた。
「なによ、それ。悠然としてるわね。好きだったんじゃないの?」花咲君が笑った。
「そうやって、絶対に教えてくれない」
「大橋は、九条に憧れていたんだと思うけど。どうしても気になっていたようだし。九条は、多分……」
「なによ?」
「初めての経験だったんじゃないかなって思うけど」
「あら、九条君なら、彼女ぐらいいくらでもいたでしょ?」花咲君が笑って答えていなかった。
「違うの? そう言えば、大学に来る前は、同じクラスになったことは?」
「あるよ」
「なんだ、あるんじゃない」
「あるよと言う程度だよ。相川と同じ」
「ああ、あいつね」
「同じクラスになったからと言って、ほとんど話さないまま行く場合も多いと思うけど」
「あら、うちはないわよ。牛美なんて、クラスが違っても迷惑をかけてきたわよ。失礼な子だった」
「まだ、怒ってるんだ?」
「あの子が言って歩いてるからよ。負け惜しみでね。わたしがインフルエンザにならなくても、安修しか受からなかったなんて、失礼な。あの子にだけは言われたくないわよね」
「お互い様だと思うけど」
「なによ」と食って掛かっていた。
「君たちの場合は、片方が穏やかにならない限りは、言い合いが続く。良い相性かもね」
「どこがよ」
「お互い、相手を馬鹿にしてるところが」千花ちゃんが黙った。
「そうね、そうかもしれない」
「やめたほうがいいね。君が言うことを放棄したら、相手も君には言わなくなる」
「君に『は』?」
「そう、君に『は』だ。君以外には言うだろう。ただし、相手に面と向かっては言わないかもね。裏でぼやくタイプかもしれない」
「そうかもねえ。あなたは鋭いわ。そういうことを教えてくれた人なんていなかった」
「そう?」
「そうよ」
「君が少しは考えてくれるようになって、うれしいよ」
「私と付き合って」
「無理だ」
「ほら、すぐに断ってくる。やめてよ。少しは女性として見て」
「無理だよ」
「もう、面白くないわね」
「前に教えたはずだ。恋人として求めている部分は弱いから。僕には恋愛感情ではなく」さえぎって、
「分かってるわよ。でも、好きだと思う」と千花ちゃんが言いきった。
「好きじゃないと思う。君がほしいのは男としての僕ではないから」千花ちゃんが困った顔をしたあと、
「あなたは本当に鋭いのね」しばらく経ってから、
「弱音が吐けるのよ、あなたには」花咲君は黙っていた。
「言いやすいの。とっつきにくいなんて言われたことがあるし、弱音なんて、はけない性格なの。でも、あなたには言える」花咲君が笑った。
「そうやって笑ってくれるからね。こういう自分でいいと思ってるのに、周りは変な目で見るし、だから言えなくて」
「そう」
「『犬花』なんて、あの子が呼び続けたわけも分かって、裏で『鼻血』なんて隠語で呼んでいたのもショックよ。でも、当たっていることもあるものね。あの子が言った通りよ。私、第一希望にインフルエンザで落ちたわけじゃないのよ。そう言ってごまかしたかったのかもしれないわね。この学校に来て、あなたに出会うように運命が決まっていたのかもね」
「そうか」
「必然だったのね。そう思うわ。あなたと出会えて、無理して虚勢を張ったりするようなのは嫌がられるって気づいて良かったのかも。あれだけ、ズタズタにされるとさすがに堪えるわ」
「君がそういう心境になってくれてうれしいよ」
「私、あなたに惹かれているわ」
「それはさっき言ったように」
「分かってる。その部分は否定できないけれど、彼女の存在が今も怖いのよ、私」
「彼女?」
「大橋さん。あなた、前に積極的にそういう関係にはなりたいとは思ってないと言っていたけれど、でも、あなたが大橋さんを見る目には恋愛感情も含まれているような気がしてならないの」
「そう言われても、困るけどね、俺も」
「今は彼女のほうに向けられているその気持ちを、いつか必ず私のほうに向けさせてみせるわ」
「君はつくづく勝気だね」
「彼女と足して割ったらちょうどいいというんでしょ」
「それぞれがお互いに自分を磨いていくしかないと思うけど」
「あなたには私のほうが合っていると思うんだけどな」
「それは君の願望が入ってる。僕は彼女のほうが見ていて楽しい」
「もう、嫌だな。やっぱり、彼女は気に入らないわ」と言ったので花咲君が笑っていた。 |