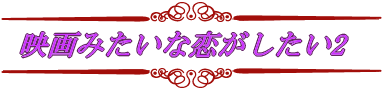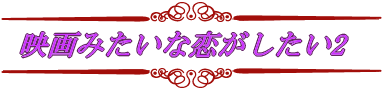「僕が言ったことを、要約してみて」
「え、私が?」
「僕の言ったことをどれぐらい理解しているのかを知りたいので、よろしく」
「よろしくって、だって、よくわからないわよ。結局、何が言いたいの? なぜ、私が悪くなるのよ」
「そこの部分だよ」
「え、どこ?」
「なぜ、私・が・悪・く・な・る・の・よ」花咲君がかなりゆっくり、一音一音発音した。
「え、っと、あの」千花ちゃんが戸惑っていた。
「君のプライドを守るために、自分は悪かったとは思いたくはない。その気持ちの強さが、反省できない理由。反省することから逃げている」
「逃げて?」と言いかけて、
「ないわ」とつづけたけれど、戸惑っていて、
「自分は悪くない、一方的に言われたくない、そうだ、そんなことを言う人が間違っている。そういう形に変えてしまう癖を見直さないとね」
「くせ?」
「そう、くせだ。考え方のくせ。自分は悪くなかったはずだと思い込むくせ」
「そんな癖は……ないわよ」最後のほうは声が聞こえないぐらいだった。
「思い当たるみたいだね」千花ちゃんが仕方なさそうにうなずいた。
「高校時代、ある女の子に言われたわ。ただ、その子、口は立つけれど、成績は良かったけれど、不器量で走るのがものすごく遅かったのよ。そんな子に言われたくないわよ」花咲君がじっと見つめて、
「他の人には言われたことは?」と聞かれて、仕方なさそうに、
「高校時代の男友達に、ほら、あなたも知っているあの人よ。学園祭準備のときにもめたときに、少しだけ、少しだけよ、言われたことはあるわ」花咲君がため息をついた。
「なによ?」
「牛木さんのときと同じだね。君はやはり、そこの部分は変わらないんだな」
「どういう意味?」
「注意した相手のレベルで、判断するってこと。つまり、君は認めたくない相手に、あれこれ自分のダメだしされると、腹が立って、あいての欠点に注目し、『そんな人が、この私に注意するなんて、だから、気にしなくてもいいわね』そうとらえるみたいだね」
「は?」千花ちゃんが戸惑いながら、
「あら、そう考えるのが普通でしょ。だって、不器用な女と、不器量な女に、何か言われたい人なんている?」反対に聞き返した。
「違うと思う」
「何が違うって言うのよ」
「不器量とか、馬鹿にしたり見下したりするような形容は、聞いていて気持ちのいいものじゃないから、次から僕の前ではやめてほしい。とりあえず、解説させてもらうと、君はせっかく注意してくれたのに、その行為を無にしてる。『この私がどうして注意されなくちゃいけないの? ああ、そうだ、相手がおかしいんだわ。わたしは悪くないのに』そんな感じでとらえてしまい、怒り出す、相手に言われたことが納得できなかったために、注意してくれた相手の欠点を探して、『そんな相手が私に注意するのがおかしい』と解釈を変えてしまうんだ。つまり、せっかく注意してくれたのに、君のほうがその気持ちを台無しにしてしまっているんだよ」
「え、だって」
「もう少し黙って聞いてくれないか。相手は君に注意するのに、多分、考えたと思う。君のような怒り出すタイプの人に注意するのは、怖いと思われる」
「怖くないわよ」と怒鳴った。
「僕は怖いと感じるよ。怒鳴られたらね」かなりゆっくり言われて、
「ご、ごめんなさい」声が小さかった。
「謝るときはもう少しはっきりと謝ってくれた方が、お互いが気持ちがいいと思うけれど」
「え、でも」と戸惑っていた。
「それに反論させてもらうけれど、私のために言ってくれたと言うより、私を馬鹿にしたくて言っていた子もいたわよ。注意よりけなしたいって意識が強い子。牛美、いえ、敦美もそんな感じだったわ」
「そう言うのは聞き流せばいい。それは誰でもしていることだ。僕が言っているのは、君のためを思って言っている人の注意のほうだから」
「そう」
「君はどうでもいい、やっかみの言葉と、本当に君のためを思って言っている言葉の区別がつけられないのかもしれないね」
「え、そんなことはないわ」
「でも、君は注意してくれた内容が正しいのかを検証することもせずに、相手が悪いから聞き流しておけばいいに変えてしまった。どうでもいい話にしてしまい、もちろん、反省なんてしないから、君が間違っていても、そのままだった。そうして、今、高校時代の人たちには距離を置かれ、大学でも距離を置かれてしまって、それなのに、そういう態度の人たちのほうが間違っていると思い込んでいる。君が正しいのなら、誰かがかばってくれるだろう。でも、そういう人は現れていない」と言われて、千花ちゃんがショックを受けて、うなだれはじめ、花咲君がそれを見ていた。
「今、言ったことに関して、質問があれば、どうぞ」
「質問って、言いたいことは山ほどあるわ。でも、それを言うと、あなたが帰ろうとするから、言えないだけよ」と言いながら、涙が出ていた。しばらくしたら、泣き出して、
「泣いてなんていないわ。これは気のせいよ」と拭った。でも、それから、涙が止まらなくて、千花ちゃんが慌てて立ち上がってトイレに行ってしまった。
|