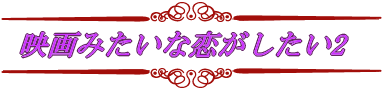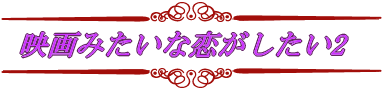「あなたと違っているの。なんていうか、こう、違っていて。一緒にいると楽なんだけれど……」
「続きを言えよ」
「楽なんだけれど、男性として意識しないと言うか。そんな感じ」
「ふーん」かなり黙ってしまった。
「ごめん、変なことを言って」
「いや」それでもかなり黙ってしまい、
「何か言ってよ」と提案した。
「いや、なんて言っていいか、俺も分からない。お前の感覚の問題だし」
「あなたにだって女性として、ドキドキしない人もいるでしょう?」
「ほとんどかもな」
「え、そういうものなの?」
「仕方ないだろう。女性としてドキドキしてしまうようなら、お前も困るだろ」
「そうなんだけれど」
「お前はいないのか? お前の周りで」と言われて、九条君を見た。
「なんだよ?」
「良く分からなくて。男性として見てる場合とそうじゃない場合と、そこまで区別している訳じゃないし。ただ、あなたのことはずっと見てたから」
「え?」九条君が驚いていた。
「不思議だね。どこに違いが出るんだろうね。好みのタイプとか、そんな感じなんだろうか?」
「そう言われても。俺も、そう言われたら、女の子としてかわいいと思えるけれど、『恋愛対象じゃないな』と思うときもあるよ」
「その違いって、区別してる?」
「そう言われたら、分からないな」
「だから、うまく言えない。言う必要もないかと思って、言ってないけれど、千花ちゃんにも言っておいた方がいいのかな。そうしたら、誤解されないし」
「無理だろ。あるときを境に男に見える瞬間もあるかもよ」
「どんな時?」
「女が男を騒ぐ瞬間だろ。テレビとかでアイドルを見る時とか。映画俳優を見る時とか、相手が注目されていて輝いて見えるとき。そんな感じじゃないか」
「スポーツ選手の場合も当てはまるね。そうか」とため息をついた。
「今度はなんだよ?」
「うーん、ある人がスポーツ選手に憧れているみたいだから」
「猿林か」
「え、なんで」と言ってから、慌てて黙った。
「猿林は、なんとかって言う、安修の先輩に憧れて、見に行ったみたいだな。甲羅がそう言ってた」
「そうか、それでね」
「でも、無理だろうな。猿林とは付き合いそうもないんじゃないか」
「どうして?」
「ミーハーな感じで寄ってこられたって、相手も困るだろう。男性として見てくれている訳じゃないから」
「え、違うの?」
「記事に載ったから行っただけだろ。猿林ならありえるから」返事できない。
「高望みしすぎてるんじゃないか? 高校時代から、そうじゃないかって、甲羅が言ってた」
「なんで? 甲羅も男子校出身だから、共学のそういう事情を知らないでしょう?」
「甲羅は付き合う女の数が多いのを忘れてるだろ。付き合ってきた女の中にはそういうことをぺらぺら話す子もいるからね」
「そう言われたら、そうだったね」
「猿林はお前たちのグループの誰かで手を打っておけばいいんじゃないかって、甲羅が言ってたから」
「とても、本人には言えないんだけれど」
「なんで?」
「恋人になりそうなのは近くに居ないって、サリがぼやいていたか」
「なるほどな。それじゃあ、一生無理かもな。花咲と犬童が付き合うのと同じぐらいに」
「だから、それも返事ができない」
「花咲はお前と付き合うほうが自然だからな」
「みんなに言われるなあ」
「それはそうだろ。俺より似合っているそうだから」
「え、そう?」
「俺に聞くな。お前たちが話してるとさ、なんだか空気感が違う。恋人同士見えるのが面白くない」
「どこが?」
「だから、俺に聞くな」と怒っていた。
|