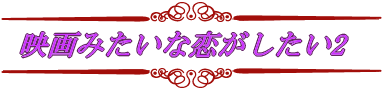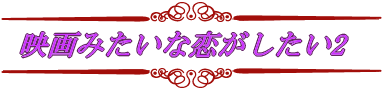海里ちゃんと合流して、
「相川は懲りないと思うわよ」とエミリに声をかけていた。
「それはあるかもな。男女の関係にまで発展してるのに、『恋人じゃない』と言い張る時点で、もうダメだろ」
「えー、それって卑怯だって」近くに座った女の子たちが、それを聞いて、
「相川の株は甲羅より下がったね」と言ったために、
「え?」とそばにいた人が驚いていた。そちらを見たら、九条君といつも一緒にいる人たちで、
「あら、なんだ、いたんだ?」とそっけなく言われていた。女の子たちの目線はとても冷たくて、誰もフォローをしてなかった。相川のことであれだけ怒った後だから、その勢いもあって、機嫌がかなり悪そうで、誰も取り繕うとしなかったため、
「ひょっとして、俺たちって評判悪い?」と確かめていて、誰も何も答えず、シーンとなっていた。かなり黙った後、こちらを見るのをやめて、そのグループの人たちが極まりが悪そうな顔のまま、黙々とご飯を食べていた。
千花ちゃんは段君たちに話しかけていた。渋々ながらも応じていて、主に仲島君だけが応えていた。花咲君が合流したけれど、彼は段君に話しかけて、違う話をしだして、
「あなたも参加しなさいよ」と千花ちゃんが言ったけれど、笑って、
「そちらで盛り上がって」と断っていた。とたんに面白くなさそうにしていたため、
「やめたほうがいい」と上久保君が注意した。
「え?」
「そういう顔を露骨に出すのはやめたほうがいいと思う。一緒にいる人たちは不愉快な気分に……させられるから」
「え? ああ」と千花ちゃんが花咲君を見て、彼がうなずいた。
「そうね、気を付けるわ」と言ったため、男子学生たちが驚いていた。
「私、こういうところがいっぱいあるのね。いくらでも注意して」
「いや、無理だ。怖い」と正直に蓮池君が言ってしまったために、一瞬、空気が凍った。でも、花咲君が、
「それが事実だから受け止めないとね」と優しく千花ちゃんに教えた。
「そう、そうなのね。だから、誰も……話しかけないのね」と珍しく落ち込んだ姿を見せたため、
「ごめん」と蓮池君が謝った。
「そうだな、落ち込むなよ。悪かった。言いすぎた」と仲島君も言い出して、
「ごめん」と千花ちゃんが謝ったため、みんなが驚いていた。ただし、小さな声だったので、
「聞こえなかった」と花咲君が笑った。
「笑うことはないじゃない」と千花ちゃんが面白くなさそうで、
「少し、弱ったほうが、俺たちはうれしかった。さっきの態度、戻ってきてくれ」と仲島君がからかうように言って、
「え?」と千花ちゃんが驚いて、みんなが笑ったために、千花ちゃんもつられて笑っていた。
電話が掛かってきて、
「緊張する」と九条君に言ったら、
「お前はすぐにそれだな」とあきれていた。
「だって、嬉しさと初めての経験だし」
「なんで?」
「彼氏と一緒にそういうところに参加すると言うのは映画みたいだから」
「お前は、本当に映画と混同するんだな」
「いいじゃない。それぐらい」
「映画を現実にする努力ぐらいしろ」
「ごめん、無理だ」
「ほらな、弱気だ。俺たちを見返すためにがんばるんじゃなかったのか?」
「がんばったじゃない」
「まだまだ、発展途上」
「うるさいの。じゃあ、がんばって綺麗になるから」
「がんばれよ」
「あなたもね」
「なんで、俺が?」
「お兄さんを見返したいんじゃないの?」と聞いたら黙ってしまった。
「ごめん」
「俺さ。あの人と比べられたくないと思いながら、俺も方向違いなことをしてたかもな」
「なんで?」
「俺は俺。あの人はあの人。お前と同じだな。自分を磨けってことなんだろうから」
「なるほど」
「明日は頑張れよ」
「あの、あなたと一緒に行くんだけれど」
「俺はリードしない。フォローもできないから、期待するな」
「あのね。どうしてもっと優しく言えないの。それは期待しないでくれ。でも、がんばって、フォローぐらいはしてみると言ってよ」
「無理だよ。俺はそういうタイプじゃない。だったら、花咲と行けば」
「彼は行かないかもよ。そういうハイソなところには」
「ハイソか? いとこの家に行くぐらいでおおげさな」
「ほらね、感覚が違う」
「ま、綺麗にしておいてくれ。60点以下だと連れて行かないから」
「え?」
「嘘だよ。それぐらいは目指せ」と言って電話を切ってしまった。今は何点なの?……と聞きそびれた。
|