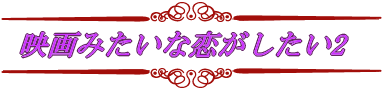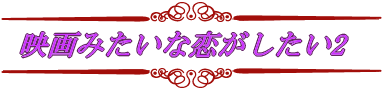「エミリ、そのうち、彼氏ができるだろうから、大丈夫だと思うけどなあ」
「今は彼氏はいないのか?」
「候補はいるみたいだよ。ただ、あなたのかるーいお友達との一件でちゃんと確かめたいんだって」エミリは一時期、甲羅と付き合って、手帳を見て、怒って顔をひっかいて、それきりだった。ただ、それを表には出していないため、知らない子もいる。
「そうか。悪いな」
「あなたが謝らなくても」
「甲羅も身近でやると評判が悪くなりそうだけど、そういう部分はごまかせると思っているようだから」
「そう。確かに取り繕うのは上手そうだね」
「俺は苦手だからな、そういうのは」
「それは私も同じだ」
「それより映画の宣伝しておけよ」
「え、やだよ」
「でも、同じことを繰り返したら、今度こそ立ち直れないぞ、あいつら」
「そうかもねえ」シオンさんにその時のことをこっそり教えてもらっていた。高校での学園祭で、だれも見に来てくれなくて、たまに人が立ち寄ってもすぐに行ってしまったという。そういう苦い思い出があるから、顔が良い九条君に高校時代から出演依頼していたという。女性が見てくれるかもしれないからと。
「動機が不純だ。顔がいい人を配役したら女性が見てくれるかもしれないからなんて」
「女の方が露骨かもな、そういうのは」
「え、そう?」
「それはあるさ。顔がいいやつ、女が認めるやつが言う言葉とそうじゃないどうでもいい奴と明らかに聞く態度が違うからって。映画のスタッフで参加した連中が何度かぼやいていたぞ。明神の家に泊まった時に、聞かれたからなあ」
「なにを?」
「どれぐらい告白されたかってこと」
「ああ、なるほど。そういえば、そういう話は聞いてない。どうだったの?」
「話してあるだろ。ないよ。甲羅がナンパして、それで一緒にデートする程度。通学途中でラブレターを渡された男は何人かいたけれど、さすがに話しかけられても、困るしな」
「学校の先生がうるさいとか?」
「違う。先生には言わなければバレないさ。そうじゃなくて、同級生だ。彼女が欲しいと思ってるやつからするとうらやましいのか、うるさくなるからな。俺も何度聞かれたかわからないし」
「そういえば、そう言っていたね」夏休みのデート中に、そう教えてもらっていた。映画のスタッフに私のことを聞かれて、デートしているのかどうかとか、メールはどれぐらいしているとか、かなり聞かれて困ったらしい。
「そういう話はしてなかったから、気づかなかった」
「さっきもそういう目線で見ていた。俺たちが付き合ってるかどうかなんて、あいつらには関係ないと思うけど」
「そう」とため息をついた。あれだけ何度か見られたらさすがに気づいてしまう。そうか、邪推しているんだな。
「シオンさんのことを気になっているようだから、私は対象外だろうし、そういうのは気にしてないかと思って」
「ああ、無理。あの二人、付き合ってるらしいぞ」
「どの二人?」
「明神と長船」
「嘘だー。だって、二人とも友達感覚にしか見えないよ」明神君はカメラ担当、シオンさんは脚本担当で、映画を撮っている間、言い合いも多かった。
「長船はさらっとしてるからだろ。女性として見ろと言われても、俺でも困るぐらいだし」シオンさんはかわいらしい容姿をしている。背は低め、目はくりっとしてかわいいと男性も女性も思う人が多いだろう。ただ、服装や髪形には気を使わない。カジュアルで着心地の良さそうな物しか着ていない。男性と混じって後ろから見たら、分からなくなるぐらいだった。
「付き合ってるのか。そうなんだ、知らなかった。意外だなあ。てっきり、監督の方と仲良しさんだと思ってた」
「ああ、あいつは無理。理屈っぽいから」
「九条君に言われたら、向こうも嫌じゃないの。あなたも同じような部分が」
「お前が考えなさすぎるから、そう見えるだけ」と淡々と言われてしまった。
「どうせ、考えなしで行動するところがありますよ。すみませんね」と横を向いた。彼とはこういう部分で価値観が合わない。怒られてばかり。当然、私は面白くなく、そうして……黙る。
「ごめん」しばらくしてから彼が謝ってきて、
「ごめん」とこっちも謝った。お互いにさすがに黙っているのは気まずいので謝るけれど、そのあと、やはり会話が続かない。花咲君と違って彼は話しづらいところがある。
「それで、高校時代のやつらにも宣伝しておけ。どうせ、草刈はいっぱい言って歩いているだろう?」
「そうだけどね」エミリは聞かれるとその話をうれしそうに話していた。いまさらだけど、私は恥ずかしくて聞かれても、どう答えていいかわからない。「見てね」とも、「すごくいい映画だよ」とも言えない。完成品を見せてもらってないのだから、当然だけど。
「見たかったな。完成したものを」
「甘い。『ほぼ完成している』とあいつらが言ってるってことは、『ほぼ』であり、まだ、納得してない部分があるから見せられないだけだろ、どうせ」ありえるなあ。まだまだもめていた。シオンさんが見せたい場面と監督がこだわっている仕上がり感が違うらしい。カメラの明神君も自分のこだわりを持っているようで、その辺でもめているようだった。
「なんだか、あれで大丈夫なんだろうか?」
「いいだろ。記念になってね。いい映画になってるさ。恋愛映画なんだから、実際に」と言われて、呆れて彼の顔を見た。
「ああいうのは了解を取ってからにしてよ」
「うれしかったくせに」
「あのね。そういうのはちょっと困るよ。あれだけ大勢に囲まれていて」
「離れていただろ」
「いや、そういう問題じゃなく」何度、こうやって言い合いしたんだろうな。彼は絶対に折れてくれない。必ず反論して、自分の言いたいことを言ってくる。とてもじゃないけれど、男性と仲良くデートして、なんて気分にはなれない。「日の当たる道」の麻耶って、映画が終わった後、どういうデートをしたんだろうなあ? あの続きが見たいなあ。私たちは、こうやって喧嘩してデートしても、甘い雰囲気にはなりそうもないなあなどと考えながら、ため息をつくしかできなかった。
|